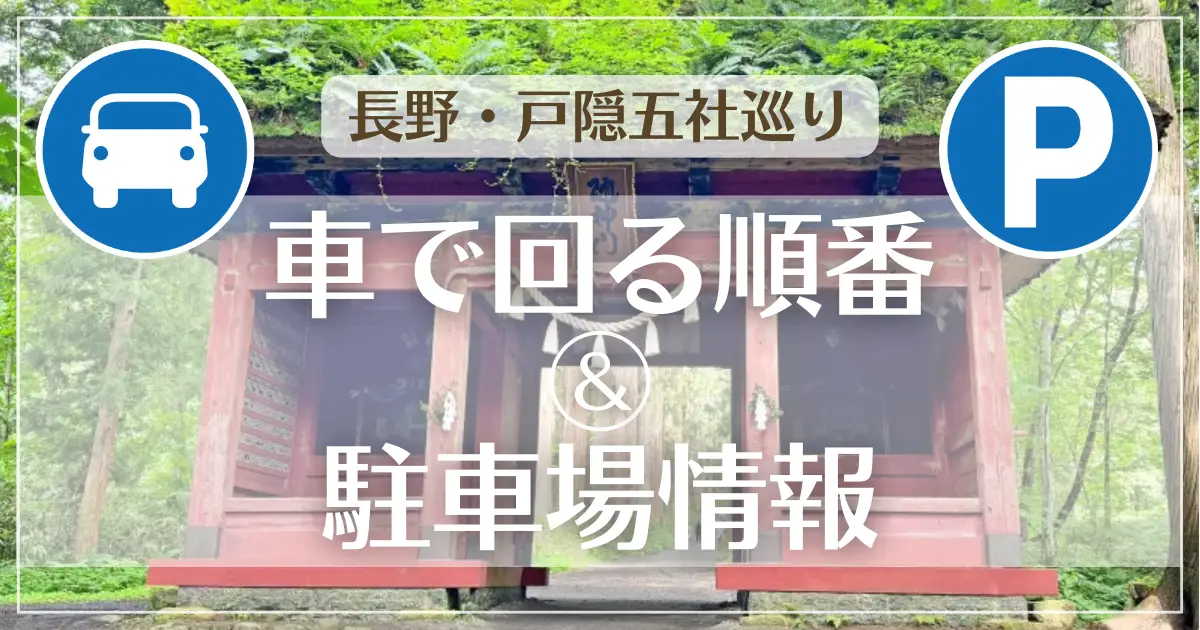長野県・戸隠(とがくし)には、霊山としての深い歴史と自然の美しさを併せ持つ「戸隠神社」があります。
ここには5つの神社が点在していて、「五社巡り」として多くの人が訪れており、我が家も車で順番に参拝をしてきました。
今回は夜中に家を出発し、朝6時ごろから「戸隠神社の五社巡り」を開始。
下調べ時に、繁忙期の渋滞はかなりのひどさという情報が多かったため、現地へ着くまで内心ドキドキでしたが、早起き(夜中起き?)が功を奏し、スムーズに参拝を終えることができました!
- 車で五社巡りしたいけど、回り方はどの順番が良いの?
- 持ち物や服装はどんな準備をしたの?
- 戸隠神社にはどんな歴史があるの?
など、戸隠神社の歴史や我が家が実際に回ったルート、服装・持ち物の注意点や神社の様子などを現地で撮影した写真を交えながら紹介していきます。
これから初めて戸隠神社 五社巡りを車で回ろうと考えている方は、ぜひ参考にしてくださいね!
(五社巡りの駐車場記事はこちら)
「戸隠神社・善光寺」周辺の
人気宿 10選
※ホテル名クリックで楽天トラベルに移動します
他にも沢山のホテルがあるので、割引クーポンやポイント還元がお得な楽天トラベルで探してみてくださいね。
>>楽天トラベルで他のホテルを探してみる
▼旅行予約前に要チェック▼
\ 楽天トラベルお得情報!/
奥社・九頭龍社は例年1月上旬から4月後半まで閉殿期間となっていますので、ご注意ください。
目次
戸隠神社の歴史的背景は?
最初に戸隠神社の歴史的背景を簡単にご紹介します。
長野県・戸隠は、神秘的な自然と深い信仰の歴史が息づく地として有名で、中でも「戸隠神社」は、奥社・中社・宝光社・火之御子社・九頭龍社の五社を巡拝する「五社巡り」で知られています。
戸隠神社の創建は、古事記や日本書紀に記される「天岩戸(あまのいわと)神話」に由来し、岩戸に隠れた天照大神を引き出した神々の活躍の舞台となったとされるのが、この戸隠の地。
天照大神が岩戸に隠れ、世界が闇に包まれた時、力自慢の神・天手力雄命(あめのたぢからおのみこと)が岩戸を開き、再び世に光が戻ったという有名な神話です。
こうした背景をもとに創建された戸隠神社は、平安時代から修験道の聖地として栄え、近年はパワースポットとしても世界中の観光客から注目を集めている神社となっています。
 ポチップ
ポチップ
五社巡りを車で回る順番は?
戸隠神社公式サイトにて確認しましたが、五社巡りの順番は特に決まりはないそうです。
我が家の場合は、戸隠神社の南に位置する長野自動車道から向かったため、最初に到着する「宝光社」から参拝を開始しました。
下記に、我が家の大体の時間帯を記載してありますが、写真撮影が多いので、ゆっくり歩いた場合にかかる時間と思ってくださいね。
五社巡りの順番
- 宝光社(6:00前着)
- 火之御子社(7:00前着)
- 中社(7:40ごろ着)
- 奥社入口駐車場へ(8:20頃着)
- 九頭龍社(9:20ごろ着)
- 奥社(9:30ごろ着)
- 奥社入口駐車場へ(11:00頃着)
※⑤⑥は奥社入口駐車場からかなり歩きます
(撮影時間含めて片道50分ほど。混雑時は奥社の階段待ち時間が1時間以上必要な時もあり)
- 火之御子社:授与所無し
(御朱印は、参拝後に中社または宝光社にて)
- 九頭龍社・奥社:授与所同じ
我が家は御朱印集めをしていないため、渋滞回避をしようと、早朝6時頃から1社目の参拝をしましたが、もし、御朱印集めも目的で行かれる方は、各神社の授与所の受付時間は9時からとなっていましたので、参拝開始時間に気を付けてくださいね。
なお、授与所開設期間は季節により異なりますので、正確な受付時期・時間は公式サイトにてご確認ください。
>>戸隠神社公式サイト「お知らせ」
渋滞について
ネットで見つけた地元の方の現地情報では、
- 9時頃から各神社の駐車場が満車
- 駐車場待ちの車で大渋滞が発生する
- 9時までに駐車場を確保
- 歩いて各神社巡りをする方が渋滞を回避できる
ということでしたが、正直「宝光社」に車を止めて、その後全て歩いて回るのは、ハイキングや登山に行き慣れたかなりの健脚の方向きです。
また、虫が出てくる季節は、アブが非常に多く飛んでおり、クマも出没する地域。
特に、「奥社」までは奥社入口駐車場から片道40~50分ほど歩くことになりますので、余力を残しておいてくださいね。
※写真撮影しながらかかった時間です。
※繁忙期は、最後の奥社への階段で1時間半並んだという声もネット上で見かけました。
我が家のように「参拝のみ目的」の場合は、早朝から五社巡りを開始すると、渋滞知らずで回ることができるので、オススメですよ。
駐車場について、詳しくは別記事にまとめましたので、そちらをご覧ください。
▼戸隠神社 五社巡り「旅行計画お役立ちマップ」や、当日利用した駐車場などを紹介しています
あわせて読みたい
戸隠神社 五社巡りの順番は?車での回り方や駐車場情報・現地情報など一挙紹介!
家族で長野県へ一泊二日でドライブ旅行に行ってきました。 初日はずっと行きたかった戸隠神社、二日目は善光寺へ。 今回は1日目の「戸隠神社 五社巡り」について。 車で…
五社巡り時の服装・持ち物は?
長野県の戸隠神社は、標高が少し高いため、普段街中で暮らしている場合、訪れる際には少し服装などに注意が必要となります。
大体の目安を一覧表にしましたので、お出かけのシーズンに合わせて、参考にしてくださいね。
なお、下記はあくまでも「目安」で、近年は、急に夏日になったり、夏なのに肌寒くなったりする場合があります。
お出かけ前に「天気予報」にて現地の気温を確認し、重ね着で体温調節ができるようにしておくと快適な旅になりますよ♪
※天気予報参考⇒ tenki.jp(戸隠神社天気)
天気は前日・当日に急変の可能性もあり
▼戸隠神社 月別気温と服装の目安
スクロールできます
| 月 | 平均最高気温 | 平均最低気温 | 服装の目安
奥社・九頭龍社=例年1月上旬から4月後半まで閉殿期間 |
|---|
| 1月 | -2℃ | -10℃ | ダウンジャケット、厚手のコート、手袋、マフラー、スノーブーツなどの防寒対策必須。積雪・凍結に注意。 |
| 2月 | 0℃ | -10℃ | 1月と同様の防寒装備。滑りにくい靴や防寒小物を準備。 |
| 3月 | 4℃ | -7℃ | 厚手のコートやダウン、手袋、マフラーなど。
残雪があるため、滑りにくい靴を。 |
| 4月 | 12℃ | -7℃ | 長袖シャツ、セーター、コート。
朝晩は冷えるため、ライトダウンの重ね着などで調整を。
残雪があるため、滑りにくい靴を。 |
| 5月 | 18℃ | 5℃ | 長袖シャツ、カーディガン、薄手のジャケットなど。日中は過ごしやすいが、朝晩は冷えることも。 |
| 6月 | 21℃ | 10℃ | 長袖シャツ、薄手のセーターやパーカーなど。
※天候が変わりやすいため雨具も |
| 7月 | 24℃ | 14℃ | 半袖シャツ、薄手の長袖、羽織るものなど。朝晩は涼しいため、軽い上着があると安心。
※天候が変わりやすいため雨具も |
| 8月 | 26℃ | 15℃ | 半袖シャツ、薄手の長袖、羽織るものなど。朝晩は涼しいため、軽い上着があると安心。
※天候が変わりやすいため雨具も |
| 9月 | 20℃ | 11℃ | 長袖シャツ、カーディガン、薄手のジャケット。朝晩は冷えることも。
※天候が変わりやすいため雨具も |
| 10月 | 14℃ | 4℃ | 長袖シャツ、セーター、厚手のジャケット。紅葉シーズンで冷え込みが強まる。 |
| 11月 | 8℃ | -3℃ | コートやダウンジャケット、手袋、マフラーなどの防寒対策が必要。 |
| 12月 | 2℃ | -7℃ | ダウンジャケット、厚手のコート、手袋、マフラー、スノーブーツなどの防寒対策必須。積雪・凍結に注意。 |
特に一般の観光客が増えるゴールデンウィークやお盆・紅葉シーズンは、街中と同じ服装で出かけると、かなりの気温差で風邪を引く可能性大となりますので、
(※上記商品クリックでAmazonに移動します)
など、重ね着をして、当日の気温に合わせて調整、紫外線対策ができるようにしてお出かけするのがオススメです。
ちなみに我が家はお盆休みに行ったのですが、昼間は半袖、早朝と夕方は薄手の撥水ウィンドブレーカーを羽織り、さらに昼前から雨予報だったので、念のため折り畳み傘もリュックに入れていきました。

▼鞄に入れるなら、軽くて折りたためる晴雨兼用の日傘が便利!
>>楽天市場で「晴雨兼用折畳み日傘」の写真を見てみる
- 防寒対策: 冬季(12月〜3月)は積雪や凍結が予想されるため、滑りにくい靴や防寒具の準備が必要です。
- 雨具の準備: 春から秋にかけては天候が変わりやすいため、携帯用の雨具を持参すると安心です。
- 虫&クマ対策: 夏季は虫が多いため、虫除け対策必須。クマ除けの鈴などもお忘れなく。
- 靴選び: 参道は舗装されていない箇所や階段があるため、歩きやすい靴がオススメです。
戸隠神社 五社の駐車場・御利益一覧
五社巡りの駐車場記事にも載せましたが、参拝順に駐車場やご利益などの一覧表を当記事にも再掲しておきます。
(駐車場記事はこちら)
スクロールできます
| 神社名 | 駐車場名前 | 駐車場 | 主なご利益 | 御祭神 |
|---|
| 宝光社 | 宝光社
参拝者駐車場 | 約20台
無料
24時間可 | 学問成就
女性守護
子育て | 天表春命 |
| 火之御子社 | 火之御子社
駐車場 | 約3台
無料
24時間可 | 舞楽芸能上達
縁結び
火防の神 | 天鈿女命 |
| 中社 | 中社
西側駐車場
訪問時、中社表側は
有料駐車場でした | 約100台
無料
24時間可 | 学業成就
商売繁盛
家内安全 | 天八意思兼命 |
| 九頭龍社 | 戸隠神社
奥社入口駐車場
奥社と共通 | 奥社入口P
800円/3時間
24時間可 | 縁結び
虫歯の神
水の神 | 九頭龍大神 |
| 奥社 | 戸隠神社
奥社入口駐車場 | 同上 | 心願成就
五穀豊穣
スポーツ必勝 | 天手力雄命 |
ここからはお盆休みの早朝5時半ごろに到着した「宝光社」の駐車場から、最終目的地「奥社」までの参拝ルートを当日撮影した沢山の写真を交えながら、順番に詳しく紹介していきます。
宝光社
▼宝光社参拝者駐車場(グーグルマップ)